長辺綴じと短編綴じの違い|印刷される冊子やデータの作成方法を解説
2023.04.30ネット印刷・デザイン
書類などを両面で印刷している際、裏表が逆になってしまったという経験がある方もいらっしゃると思います。
それは長辺綴じと短編綴じを間違えてしまったことが原因です。
本記事では、印刷物による長辺綴じと短編綴じの使い分けの方法についてご紹介します。
長辺綴じとは?

長辺綴じとは、用紙の長い辺を綴じる方法で、縦読みでも横読みでも視線の移動距離が短いため、文章が主体の書籍に適した綴じ方であると言えます。
長辺綴じのメリット
長辺綴じには、「縦横どちらでも視認性が高い」「開いたときに持ちやすい」といったメリットがあります。
縦書き・横書きのどちらでも視認性が高い
冊子の綴じ方には、表紙を表にしたときに右側が綴じられている「右綴じ」や、左側が綴じられている「左綴じ」などがあります。
また、「縦書き」とは文章が上から下に進む書式で、「横書き」は左から右に文章を追う書式です。
下記、右綴じ・左綴じ・縦組み・横組みの冊子における視線の動き方です。
| 右綴じ | 左綴じ | |
| 縦書き | 上から下に読み、最後まで行くと左の文章に移動 | ほとんど使われない |
| 横書き | ほとんど使われない | 左から右に読み、最後まで行くと下の文章に移動 |
長辺綴じの場合、縦組みと横組みのどちらでも視線の移動が大きくならないため、視認性が高くなるメリットがあります。
冊子を開いたときに持ちやすい
長辺綴じは冊子をめくりやすく、手に持った際も高い安定感があるといった特徴があります。
たとえば、文庫本のような小さいサイズの冊子は、片手でページを開いて支えることができます。
短辺綴じの場合は横の幅が長くなるため、広げると邪魔になる一方、長辺綴じはコンパクトに収められるため、邪魔になりにくいメリットがあります。
長辺綴じの注意点

長辺綴じには視認性が高い、冊子を開いたときに持ちやすいといったメリットがあります。
しかし、長辺綴じの冊子には下記のような注意点があるため、印刷前には注意しましょう。
写真やイラストがコンパクトになる
一般的な長辺綴じの冊子は縦綴じで製本される傾向にあります。
縦綴じは文章の視認性が高い一方、横の辺が短くなるため写真やイラストがコンパクトになる傾向にあります。
見開きいっぱいに写真やイラストを掲載しても、無線綴じのように見開きの中央部分に該当する「ノド」を開ききることができない場合、視認性が下がります。
そのため、長辺綴じの場合は文章をメインとした冊子を製本するようにしましょう。
ほかの冊子との差別化が図りにくい
日本では後述する会社案内や商品カタログといった、長辺綴じの冊子が多く製本されています。
また、ビジネス書や文庫本も長辺綴じのものが多いため、書店に並べられた際は読者に見つけられにくい懸念があります。
多くの人に冊子を手に取ってもらうために、長辺綴じ冊子の表紙はこだわったデザインを印刷しましょう。
長辺綴じで製本される冊子一覧
長辺綴じに向いている印刷物は、文字数が多い下記のようなものが挙げられます。
会社案内
会社案内とは、入社希望者や取引先などに、自社について知ってもらうための冊子で、会社概要や沿革、経営理念、業務内容などが記載されます。
作成する際、会社概要に目を通した人が見やすいように、それらの情報をコンパクトにまとめることが重要です。
商品カタログ、パンフレット
商品やサービスの情報をわかりやすくまとめた、商品カタログやパンフレットも長辺綴じで製本されます。
これらの冊子は商品の追加など、情報の差し替えが多い場合によく用いられています。
プレゼンテーション資料、企画書
社内外に対して提案を行う際に使用するプレゼンテーション資料や企画書は、A4用紙で印刷され、長辺綴じが使用されることの多い冊子です。
PowerPointなどで作られた上記の冊子は、提案を行う際には資料だけではなく補足資料をプロジェクターなどで映すことが多いです。
小説・ビジネス書
小説やビジネス書のように、文字情報が多くじっくりと読んでほしい冊子に長辺綴じが使われます。
先述の通り、長辺綴じは写真やイラストが小さくなる注意点がありますが、小説やビジネス書のように文字がメインの冊子の場合、大きなデメリットとはならないでしょう。
短辺綴じとは?

短辺綴じとは、用紙の短い辺を綴じる方法で、視線の移動距離が長いことからイラストや写真など、読者に一目で認識してもらいたい情報を掲載した書籍に適した印刷方法です。
短辺綴じのメリット
短辺綴じの冊子には、下記のように「冊子を大きく広げられる」「オリジナリティがある冊子を製本できる」といったメリットがあります。
冊子を大きく広げられる
短辺綴じの冊子は、写真やイラストを大きく掲載できるため、高い視認性を得られます。
パノラマ写真や横長の写真・イラストなどを掲載できるため、冊子を見た人に強いインパクトを残すことができます。
また、短辺綴じの冊子はページを開きっぱなしにしやすく、作業の手順や工程の説明にも向いています。
オリジナリティがある冊子を製本できる
先述の通り、日本では長辺綴じの冊子が多いため、短辺綴じというだけでもオリジナリティがある冊子となるでしょう。
また、中身についても短辺綴じの場合、写真やイラストが多用される傾向にあるため、個性豊かな冊子になります。
写真やイラストは文字情報よりも記憶に残りやすいため、読者に強いインパクトを残すことができます。
短辺綴じの注意点

一方、短辺綴じには「デザインやレイアウトが難しい」や、「扱いにくい」といった注意点があります。
デザインやレイアウトが難しい
短辺綴じは写真集や絵本のようにデザインを重視する冊子に使われる傾向にあります。
読者に強いインパクトを残せる一方、分かりやすいようにデザインをするためにはコツや工夫が必要です。
そのため、はじめて短辺綴じの冊子を製本する方はデザインやレイアウトを考えるのに苦労する方もいらっしゃると思います。
扱いにくい
短辺綴じの冊子は縦横に広げて中身を見るため、多くの場所が必要になります。
長辺綴じの場合はコンパクトに開けますが、短辺綴じはスペースを取るため、扱いにくい印象を持つ方もいらっしゃいます。
しかし、短辺綴じは開きっぱなしにしやすいため、長時間冊子を見たい方にはメリットとなります。
短辺綴じで製本される冊子一覧
こちらでは、短辺綴じで製本される冊子をご紹介します。
絵本
短辺綴じに向いている印刷物には、子どもに読み聞かせる絵本が挙げられます。
先述の通り、短辺綴じはイラストや写真など、読者に一目で認識してもらいたい情報が記載される傾向にあるため、絵本もそのひとつと言えます。
写真集・イラスト集
写真集やイラスト集なども、短辺綴じで製本されることがあります。
写真の場合は横長に撮影されることも多く、風景画や動物などは横長の写真集に使われる傾向にあります。
ほかには、自動車やバイクなど、被写体が横長のものも冊子が横長になる傾向にあります。
事務用品
メモや領収書といった事務用品も、短辺綴じが用いられる冊子に含まれます。
一般的に横長の事務用品は書いてからちぎることが想定されているため、ノドの部分に点線の切れ目が入れられているものが多いです。
また、事務用品は書き込んで効果を発揮するため、使う人が書きやすいようなデザイン・レイアウトを設定しましょう。
綴じる場所について

長辺、短辺綴じをご理解いただいたところで、こちらでは左綴じ、右綴じ、上綴じといった、綴じる場所について解説します。
左綴じ

冊子の表紙を上にした際に、綴じている辺が左側に来る綴じ方です。
左綴じの冊子を読むときは、左から右、左下といった、アルファベットの「Z」の字に視線が動きます。
左綴じで製本される冊子一覧
左綴じの冊子には、先述したようにさまざまなものが含まれます。
- 参考書
- 説明書
- 写真集
- パンフレット
- 図鑑
- 地図
- 英語・理科の教科書
- 楽譜
- フォトブック
- イラスト集
- 横書きの小説
写真やイラストが記載された冊子が製本されることが多いため、短辺綴じと併せて使われることがあります。
また、ノドを見開きいっぱいに開くために針金で綴じる「中綴じ」が使われることもあります。
左綴じの冊子を見た読者の視線の動きはアルファベットの「Z」のように、左から右、その下の行に移動します。
一番初めに左上の情報を視認することから、最も伝えたい情報を左上に記載することで、読者に覚えてもらいやすくなります。
右綴じ

冊子の表紙を上にした際に、綴じている辺が右側に来る綴じ方です。
日本では縦書きが使われることが多いため、右綴じの冊子が多い傾向にあります。
これは縦書きの文章は上から下、左上に進むといった、「N」の字に視線が動くことが要因です。
右綴じで製本される冊子一覧
右綴じも先述したように、下記のような冊子が含まれます。
- 漫画
- 小説
- 国語辞典
- 雑誌
- 国語の教科書
- 小説
左綴じと比べると文字情報が多い冊子に用いられることが多いため、長辺綴じと併せて綴じられる傾向にあります。
また、ノドの部分は開ききらなくても問題ない冊子もあるため、「無線綴じ」や「平綴じ」などが用いられます。
読者の視線は上から下、左の行に移行する、アルファベットの「N」を逆に描いたような動きで情報を視認します。
右綴じは新聞なども上から下に視線が移動するため、日本におけるさまざまな冊子に使われる綴じ方です。
上綴じ

上綴じとは「天綴じ」とも呼ばれ、製本するものによっては糊や接着剤を使用する無線綴じ、針金や糸といったものを使用する中綴じなど、さまざまな綴じ方が選ばれます。
上綴じで製本される冊子一覧
上綴じで製本される冊子には、カレンダーや伝票、メモパッドのように事務用品が含まれます。
これらはちぎったり、書き込んだりするため、点線でちぎりやすいように加工し、書き込みやすい素材で製本される傾向にあります。
上綴じ冊子の視線の動き方は左から右、下の行に行って左から右なのでアルファベットのZのように動きます。
上綴じは縦長になりやすい冊子のため、一般的にはアルファベットの「F」のように動くと言われています。
多くの人に見てもらえる冊子を製本するコツ

手間暇をかけて製本した冊子は、可能な限り多くの人に読んでもらいたいものです。
そのためには、下記のポイントを抑えましょう。
目的を明確にする
冊子には「写真やイラストに感動してほしい」や「文章をよく読んでほしい」といった目標があります。
これらの目標が明確になれば、どのような綴じ方にすれば良いかが分かります。
たとえば、写真やイラストに感動してほしい場合、広い面積で表現ができる短辺綴じが向いています。
また、文章をよく読んでほしい場合は日本人になじみが深い縦書きの文章を作成し、長辺綴じで冊子を製本しましょう。
余白を有効活用する
ぎっしりと情報が詰まった冊子は、読者に窮屈な印象を与えます。
そのため、適度に余白を設けることで伝えたい情報が明確になり、読者に「この情報は大切なことだな」と分かりやすくなります。
場合によっては、1ページに1訴求しか記載されていない冊子もあります。
おわりに
本記事では、長辺綴じと短辺綴じの特徴や印刷物の一例をご紹介しました。
長辺綴じは用紙の長い辺を綴じる方法で、会社案内やパンフレット、企画書などに用いられます。
短辺綴じは用紙の短い辺を綴じる方法で、絵本や写真集、イラスト集といった、画像をメインとした冊子を製本する際に用いられます。
上記以外にも、製本する冊子によって左綴じや右綴じ、上綴じなど綴じる方向も検討する必要があります。
読者が読みやすいように、冊子によって最適な綴じ方を選びましょう。
最新記事 by いろぷりこらむ編集部 (全て見る)
- A2サイズデータの入稿から仕上げまでの押さえておくべきコツ - 2025年7月4日
- 会議資料・セミナー用冊子を作成・印刷する際に押さえておくべきコツ - 2025年6月20日
- イベント用ウェアの印刷を依頼する際に押さえておくべきポイント - 2025年4月12日

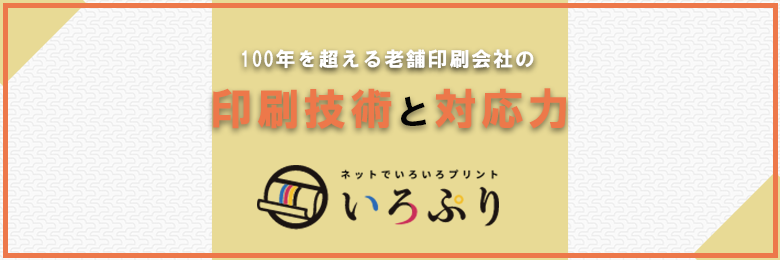
 ホチキスだけではない!本のさまざまな綴じ方をご紹介
ホチキスだけではない!本のさまざまな綴じ方をご紹介 ネット印刷と印刷会社の違いとは?
ネット印刷と印刷会社の違いとは? 【ネット印刷基礎知識】オンデマンド印刷とは?どんな印刷方法?
【ネット印刷基礎知識】オンデマンド印刷とは?どんな印刷方法? ネット印刷でよく用いられるトンボって何?
ネット印刷でよく用いられるトンボって何? クリアファイルの印刷をオーダーする際のポイントやデザインのコツ
クリアファイルの印刷をオーダーする際のポイントやデザインのコツ ネット印刷で製本する際にはどれくらいの文字数が必要?
ネット印刷で製本する際にはどれくらいの文字数が必要?