ネット印刷で製本する際にはどれくらいの文字数が必要?
2022.11.01ネット印刷・デザイン
製本する際には、読者が読みやすいように行間や文字の大きさ、文字数などに気を付けている方も多いと思います。
文庫本などをネット印刷で製本依頼する際、必要となる文字数は何文字程度なのでしょうか。
本記事では、ネット印刷で製本する際に必要となる文字数について解説します。
製本する際に必要な文字数

小説やエッセイなどを含む「文庫本」と、ビジネス書や自伝などが製本された「新書」では、下記の通り文字数が異なります。
文庫本
文庫本の場合、1冊あたりに必要な文字数は10~12万字、1ページあたりに必要な文字数は600字程度です。
そのため、ページ数は最低でも166ページとなります。
400字詰めの原稿用紙の場合、250枚程度が必要ですが、原稿で作成する場合は見出しや改行、段落替え、挿絵などが入るため、ページ数は少し増加します。
新書
新書は新しい本と混同されがちですが、105×173mmの本を指す言葉です。
先述したビジネス書や自伝だけではなく、政治や経済、学問などさまざまな分野で取り扱われています。
新書を製本する際、背を糊で留め、本体と別の素材で作られた表紙で包んだ、豪華な見た目で販売することが多い傾向にあります。
新書に必要な文字数は8~12万字程度で、1ページ当たりの文字数は文庫本と同様に600文字程度です。
ページ数は最低でも133ページ、400字詰めの原稿用紙で作成する場合は200枚程度が必要となります。
読みやすい文章を作成するためのコツ

こちらでは、読みやすい文章を作成するためのコツをご紹介します。
行間
行間とは、縦読みの場合は左右の列との間を、横読みの場合は上下の行との間にある空間を指すもので、読者が読みやすいように工夫をする必要があるもののひとつです。
行間は広すぎると次の文章を追いにくくなり、狭すぎると読者に窮屈な印象を与えてしまうため、全体的に読みにくくなります。
読者がよみやすくなるように最適な行間の設定が必要です。
一般的な冊子では、文字サイズの1.5倍程度の行間が取られています。
たとえば、文字サイズが11の場合、行間は16.5となるため、行と行の間に文字サイズの半分にあたる余白が取られているということになります。
文字のサイズ
文字のサイズはpt(ポイント)という単位で表されます。
一般的な冊子では文字サイズは8から10ptに設定されていることが多いです。
しかし、大きな冊子や高齢者が対象の書籍、教科書などの場合は少し大きめの10~14ptが使われることがあります。
余白
余白は文字と紙片の間のスペースを指す言葉で、ページ全体に余白を設けず文字や絵が印刷されていると、裁断時に文字が切れてしまう可能性があるだけではなく、手に取っている箇所が読めないといった問題が発生します。
余白が設けられている冊子は視認しやすく、見栄えが良くなります。
また、余白部分にはページ数や見出しなどを記載することができるため、見やすさ以外の観点でも余白を設けることをおすすめします。
製本する際に求められる冊子のレベル

先述の通り、1冊あたりの冊子に必要な文字数は10~12万字ですが、ただ指定文字数を記載するだけでは読者を惹きつけることはできません。
そのため、執筆・製本時は下記のポイントに注意しましょう。
執筆前に構成を考える
冊子を執筆する際、タイトルや見出し、記載する内容などの構成を考えておきましょう。
執筆前に考えておくべき構成の一例は以下の通りです。
- 本のタイトル
- 章タイトル
- 節タイトル
- 見出し
構成を考えるメリット
構成を考えるメリットには、「文章全体に統一感が出る」「章や節、見出しごとに文章を作成することができる」といったことが挙げられます。
構成を考えないまま執筆すると、記載内容にブレが生じたり、執筆が進まなくなったりします。
あらかじめ構成を考えておき、伝えたいことを明確にすることで文章全体に統一感が生まれるため、記載内容にブレがなくなります。
また、1日で10万文字以上を執筆することは難しいため、日数を分けて執筆することになりますが、タイトルや見出しを考えずに執筆した場合、何をどこまで書いたのかが分からなくなります。
翌日以降でも進捗状況を確認できるように、執筆前には必ず構成を確認しておきましょう。
執筆時のコツ

冊子を執筆する際のコツとしては、下記が挙げられます。
難しい言葉は極力使わない
冊子を目にする方は、専門的な知識を持つ方ばかりとは限らないため、冊子にはできるだけ難しい言葉を使わないようにしましょう。
専門誌など、難しい言葉を使う必要がある場合、余白部分や章末に注釈をつけることで、読者の理解を補助することができます。
また、文章だけでは言いたいことを伝えられないと思ったら、イラストや図形を用いて説明することも有効な手段です。
漢字とひらがな、カタカナの比率に注意する
文章のなかに含まれる漢字が多すぎると読みにくいだけではなく、難解なイメージを読者に与えてしまいます。
また、ひらがなやカタカナが多すぎると稚拙なイメージを持たれる可能性があるため、文章内で使う漢字、ひらがな、カタカナは読みやすいように比率を考慮しましょう。
一般的には、漢字:ひらがな:カタカナ=2:7:1が良いとされています。
1文を短くする
1文が長いと読むのが面倒になったり、意味を理解しにくくなったりします。
そのため、1文はできるだけ短くし、1文で伝えることは1つか2つに絞りましょう。
敢えて文章を長くするといった方法もありますが、読者の理解を置き去りにしないように、できるだけ短い文章で作成することをおすすめします。
一般的な目安としては1文あたり40文字から60文字と言われています。
同じ言葉は重複して使わない
先述した難しい言葉を使わず、漢字とひらがな、カタカナの比率を注意し、1文を短くしても、同じ言葉を重複して使用すると読者は違和感を持ちます。
たとえば、文章の終わりに使う「です。」や「ます。」が連続したり、特定の単語が頻出したりといったことが挙げられます。
どうしても同じ言葉を連続して使う必要がある場合、「こそあど言葉」や「先述の」といった、言い回しを変えてみましょう。
無くても意味が通じる言葉は削る
文章のなかには、記載が無くても意味が通じるものがあります。
たとえば、「不必要な言葉を省く」の場合、「不必要な」が無くても何をするべきなのかが明確なため、削っても問題ありません。
不必要な言葉が多くなることにより、読者が冊子の内容を理解するための情報が多くなってしまうため、無くても通じるようであれば、省略するようにしましょう。
また、言葉を削ることによって1文あたりの情報が際立つ、といったメリットもあります。
これらを意識することで読者に理解してもらうことができ、多くのファンを得られる可能性が高くなります。
おわりに
本記事では、ネット印刷で製本する際に必要な文字数をご紹介しました。
一般的な冊子の場合、必要な文字数は10~12万字、1ページあたりに必要な文字数は600字程度と言われています。
冊子を製本する際には文字数だけではなく、行間や文字サイズ、余白などにも注意が必要です。
また、執筆する際には、本のタイトルや見出しなど、冊子全体の構成を考えてから取り掛かりましょう。
執筆時には難しい言葉を極力使わない、漢字やひらがな、カタカナの比率を考えるなど、コツを押さえておくことで読者が理解しやすい文章となります。
読む側の心を掴めるよう、魅力的な冊子づくりを心がけましょう。
最新記事 by いろぷりこらむ編集部 (全て見る)
- イメージと違うものが仕上がった場合の対処方法や責任の所在について - 2024年7月13日
- デザイン制作に苦労している方はラフ案を作成してみよう - 2024年7月13日
- 企業や商品のイメージを構築する「ブランディングデザイン」とは? - 2024年6月8日

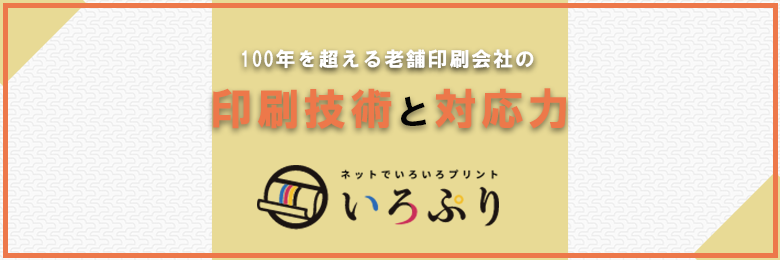
 ネット印刷と印刷会社の違いとは?
ネット印刷と印刷会社の違いとは? ネット印刷を利用するメリットと注意点
ネット印刷を利用するメリットと注意点 【ネット印刷基礎知識】オンデマンド印刷とは?どんな印刷方法?
【ネット印刷基礎知識】オンデマンド印刷とは?どんな印刷方法? 【ネット印刷豆知識】利用目的別の印刷の種類について
【ネット印刷豆知識】利用目的別の印刷の種類について ネット印刷でよく用いられるトンボって何?
ネット印刷でよく用いられるトンボって何? クリアファイルの印刷をオーダーする際のポイントやデザインのコツ
クリアファイルの印刷をオーダーする際のポイントやデザインのコツ