無線綴じ冊子印刷とは?製本方法や用途、中綴じ冊子との違いをご紹介
2022.12.11冊子印刷
「無線綴じ冊子印刷」という言葉をご存じでしょうか?
無線綴じ冊子印刷では、中綴じ冊子印刷やほかの印刷・製本方法では実現できない印刷物を作ることができます。
「それは一体どのような印刷・製本方法なのか?」と気になる方も多いでしょう。
今回はこの無線綴じ冊子印刷について、その製本方法や用途、メリットもあわせてご紹介していきます。
「無線綴じ」とは?製本方法もご紹介

本を綴じる製本方法のひとつである「無線綴じ」。
「中綴じ」の製本方法とは異なり、製本の際には糸や針金などを使わずに、接着剤のみで綴じていくため、「無線綴じ」という呼び名がつけられました。
一枚ずつ切り離されているページ用紙をページ順に並べていき、接着剤を綴じる部分に塗って表紙用紙をくるんでいきます。
背表紙があるため、比較的しっかりとした冊子に仕上げることができます。
無線綴じは、ページ数が多い冊子の製本を行う際に適している製本方法です。
「中綴じ」の製本方法とは異なり、180度見開くことはできません。
綴じる部分の付近に、文字や画像、イラストなどを配置してしまうと見えにくくなってしまいます。
左右見開きに図柄がある際は、注意しなければなりません。
無線綴じ冊子印刷のメリットは?

無線綴じ冊子印刷のメリットにはどういったものが挙げられるのでしょうか?
多くのページ数を綴じることができる
「中綴じ」では針金や糸を使って綴じていく構造であるため、ページ数が少なくて薄い冊子を製本する際には良いのですが、ページ数の多い分厚い冊子となるとこちらの綴じ方はおすすめできません。
無線綴じ冊子印刷の場合、100ページを超える冊子の製本でも問題なく綴じることができます。
ページ数が多くなるほど背幅は広く取られ、背表紙の太さによっては文字やイラストを入れることも可能になります。
背表紙を付けられる
先述でも少し触れましたが、製本に背幅があるため背表紙をつけることができます。
また背表紙は本文ページとは異なる用紙を使用して、高級感を出すことも可能です。
厚手の背表紙用紙を使うことができるため、中綴じの製本と比較するとしっかりとした製本を作ることができるでしょう。
ちなみに、厚手の表紙を使って製本を行ったものは「上製本」という呼び方をされます。
「ノド」の強度を上げられる
冊子を開いた時に真ん中に位置している綴じ代部分のことを「ノド」と言います。
無線綴じ冊子印刷では、この「ノド」部分を強化することができます。
本文ページ用紙と表紙を接着剤で接着するので、針金で製本を行う「中綴じ」と比較すると「ノド」の部分の強く固定することができるのです。
無線綴じ冊子印刷の用途は?

無線綴じ冊子印刷は、ページ数が多めの冊子を製本する際に採用されることが多いです。
そのため、教科書・情報誌・業務マニュアル・商品カタログ・論文といったような分厚い冊子物の製本時におすすめです。
背表紙の部分に文字を入れることができるという特徴を活かせるため、作品集や小説といった物にも用いられています。
また「中綴じ」の製本と比較すると、やはり冊子の「ノド」部分の強度が高いため、卒業文集・写真アルバムなどの製本にも適していると言えます。
無線綴じで製本する冊子の種類と製本時の注意点

こちらでは、無線綴じで製本する冊子の種類を、製本時の注意点とあわせて解説します。
カタログ
カタログとは、自社の商品やサービス内容を一覧化し、一度に見せることを目的とした冊子です。
商品数が多いほどページ数が多くなり、分厚いカタログになります。
そのため、各ページが抜けないように、強く固定することができる無線綴じが用いられます。
カタログ製本時の注意点
カタログを製本する際、掲載情報や表現方法、レイアウト、デザインに関する情報を社内で共有し、認識を統一しておきましょう。
掲載情報が統一されていない場合、カタログを見た人はそれぞれの情報を理解しにくくなるため、各ページで情報の過不足が無いように作成する必要があります。
また、デザインを制作している時点で共通認識がなかった場合、コンセプトが揺らいだり、社内で追加の意見が出たりといった、大幅なやり直しが発生する可能性があります。
カタログ製作の際、自社の競合となる企業が発行しているカタログを参考にすることも有効な情報収集のひとつです。
カタログとパンフレットの違い
商品紹介を目的とした冊子には、カタログだけではなくパンフレットもあります。
パンフレットとは特定の商品やサービスを記載するもので、カタログよりも薄くなる傾向にあります。
そのため、多くの商品を一度に見せたい場合はカタログ、新商品や販売強化サービスなどを見せたい場合はパンフレットといった使い分けが必要です。
マニュアル
マニュアルにはさまざまなものが含まれますが、一般的には社員や業務に関するノウハウや、業務全体の進行方法をひとつにまとめたものを指します。
社内で使われるマニュアルには、下記のような情報が記載されます。
前提となる情報
前提となる情報とは、事業方針や事業理念、事業内容といった、会社の概要に関する情報を指します。
マニュアルに記載されている業務は、前提となる情報から逸脱しない内容を記載する必要があります。
全体のフロー
全体のフローがあることで、仕事の流れを把握することができます。
マニュアルを見た人が理解しやすいように、文字情報だけではなく図面や写真などを用いて、作業に関する注意点を記載しておきましょう。
基準
基準とは業務の合否ラインや目安時間、品質といった、業務内容と提供する商品やサービスの質に関する情報を指します。
基準がない場合、従業員の業務が怠慢になったり、質が低い商品やサービスを提供したりすることになるため、生産性を上げることを目的として基準を記載する必要があります。
マニュアル製本時の注意点
マニュアルを製本する際は、「誰が」「何のために」「どのように」作業をするのかを明確にしてから、マニュアルに記載する情報を整理しましょう。
不要な情報を記載してしまうと、マニュアルを見た人が理解しにくくなり、作業効率や商品・サービスの質が低下してしまいます。
理解しやすいマニュアルを作成するために、構成や見出しを作成しておくことをおすすめします。
必要な情報を整えられた形式で記載することで、多くの人に理解してもらうことができます。
また、マニュアルは1回で完成させずに、更新を繰り返して改善するという認識を持ちましょう。
文庫本
一般的な文庫本のサイズはA6判(幅105mm×高さ148mm)で、バッグやポケットに収まるサイズであるため、電車のなかや空き時間に、気軽に読むことができる冊子です。
文庫本に記載される内容は物語や文字だけではなく、漫画なども含まれます。
価格も比較的安価で、過去出版されていた書籍が文庫サイズで再版されることがあります。
同じような情報が記載される冊子のなかには、「単行本」や「新書」と呼ばれるものがあります。
いずれも無線綴じで製本されるという特徴がありますが、単行本は文庫本よりもひと回り大きく、ソフトカバーのみの文庫本とは異なり単行本はハードカバーで製本されることがあります。
新書はビジネス書など専門分野の解説や入門書が多い傾向にある冊子で、先述した単行本よりも大きなサイズのため、ポケットには収まりません。
文庫本製本時の注意点
文庫本を製本する際、原稿を用意してから全体の構成を決めます。
その際、ページごとの役割・構成を書き込むことができる「台割表」を使うと効率良く構成を決めることができます。
文庫本はサイズが小さい冊子のため、文字数やフォント、文字のサイズに注意する必要があります。
また、ページ全体に情報を記載すると指がかかって見にくい部分が出てくるため、適度な余白を設けましょう。
卒業文集
小・中学校の卒業式に記念品として渡される卒業文集も無線綴じで製本されます。
卒業文集の特徴として、文章を作成するのは個人ではなく生徒で、取りまとめや印刷をオーダーする役割を担うのは先生です。
卒業文集製本時の注意点
先述の通り、卒業文集は個人ではなく生徒が文章を作成するため、生徒の個性や先生の指導能力により成果が左右します。
思い出に残る卒業文集を作成するためには、生徒にやる気を出してもらう必要があります。
「一生の思い出になる」「家族や親せきなど、さまざまな人が読む」といった言葉を用いて、真剣に書かなければ、という気持ちにさせることが重要です。
また、卒業文集のテーマなどは学校、教室によりさまざまですが、生徒に決めてもらうこともあります。
しかし、生徒によってはテーマを決めかねる場合もあるため、あらかじめ複数のテーマを提示しておき、そのテーマについて文章を記載してもらうことで、スムーズに作業をすることができます。
中綴じとは?

中綴じとは、表紙と本文の用紙を1枚に重ねて2つ折りにし、真ん中の折り目部分にホチキスや紐で綴じる製本方法です。
ホチキスや紐の長さによって綴じられるページ数が決まっており、一般的には50ページ程度の冊子を製本する際に使われます。
メリット
中綴じ冊子はページを開ききることができるため、ノドの部分に印刷された情報を視認しやすい点が特徴です。
そのため、商品やサービスの説明書、パンフレットといった、持ち運びを想定したものの印刷物に適していると言えます。
注意点
中綴じ冊子は1枚の紙に合計4ページ分の情報を印刷するため、4の倍数で情報を記載しなかった場合、空白のページが出てしまいます。
そのため、中綴じ冊子を製本する際、あらかじめ4の倍数でページ構成を検討しておく必要があります。
無線綴じで製本される冊子の種類と製本時の注意点

こちらでは、無線綴じで製本される冊子の種類と、製本時の注意点についてご紹介します。
企画書・パンフレット
社内や訪問時など、ビジネスシーンで使われる企画書やパンフレットは無線綴じが使われる冊子のひとつです。
企画書やパンフレットは相手に読んでもらい、契約の締結や商品・サービスの購入を目的としているため、わかりやすい構成で作成する必要があります。
また、内容によっては文字よりも写真やイラストを多く使った方が理解しやすくなります。
ページ数が少ないフリーペーパー
フリーペーパーは、地域に密接した情報や、生活に関わりが深い情報などを掲載している、無料で配布される紙媒体の広告です。
フリーペーパーを製本する際、ターゲットや配布エリアなどから配布が可能な冊数を決めておき、あらかじめ発行部数を把握しておきましょう。
発行部数が多すぎるとフリーペーパーが余ってしまうためロスが出てしまい、発行部数が少なすぎるとターゲットに配布しきれないことにより期待していた成果を出すことができなくなります。
おわりに
今回はこの無線綴じ冊子印刷について、その製本方法や用途、メリットもあわせてご紹介しました。
「無線綴じ」は、「中綴じ」で用いられている製本方法とは全く異なる製本方法になっています。
中綴じの製本時には針金・糸を使ってページを綴じていきますが、無線綴じではこれらを使わず、接着剤のみで綴じていきます。
その特徴から「無線綴じ」という風に呼ばれています。
教科書・情報誌・業務マニュアル・商品カタログといったものによく用いられているため、こちらの印刷物を作成する際には「無線綴じ」の製本方法を選択してみてください。
最新記事 by いろぷりこらむ編集部 (全て見る)
- スクラム製本のメリット・デメリットや用いられる冊子について解説 - 2024年4月7日
- 冊子に掲載するイラストのデザインがうまくなるためのコツをご紹介 - 2024年4月7日
- 印刷物にも環境に配慮したエコなものを採用してみよう - 2024年3月31日

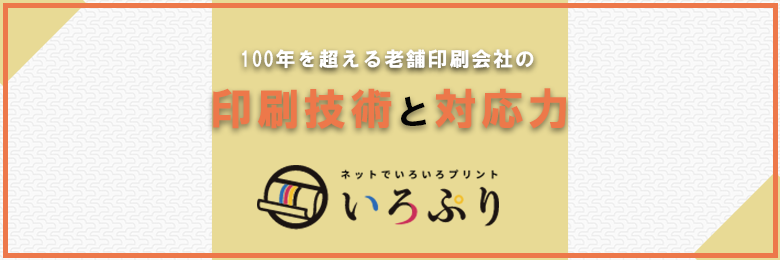
 中綴じ冊子印刷とは?無線綴じとの違いや製本方法、用途をご紹介
中綴じ冊子印刷とは?無線綴じとの違いや製本方法、用途をご紹介 【冊子印刷の知識】冊子の背表紙を作る方法について
【冊子印刷の知識】冊子の背表紙を作る方法について 冊子に使用する「ノンブル」の正しい付け方や印刷時の注意点をご紹介
冊子に使用する「ノンブル」の正しい付け方や印刷時の注意点をご紹介 冊子に使用するソフトカバーとハードカバーは印刷や製造方法が違う?
冊子に使用するソフトカバーとハードカバーは印刷や製造方法が違う? 【ネット印刷基礎知識】冊子・本における「扉」についてわかりやすく解説
【ネット印刷基礎知識】冊子・本における「扉」についてわかりやすく解説 冊子の自費出版とは?印刷を依頼する際の注意点などをご紹介
冊子の自費出版とは?印刷を依頼する際の注意点などをご紹介